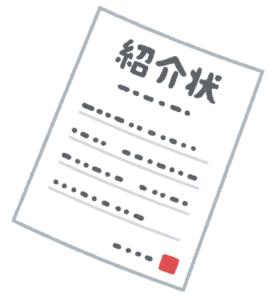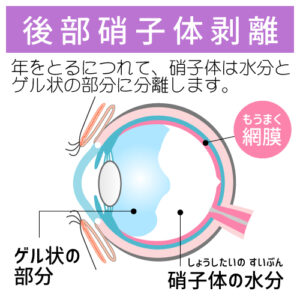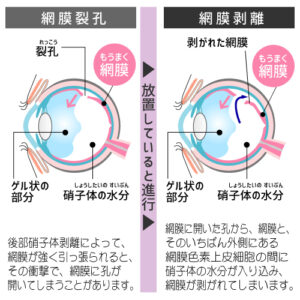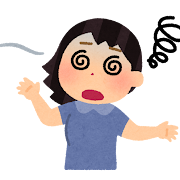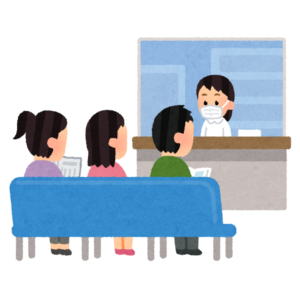近年、運転免許更新の時期になると
「どうしても免許を更新したい!!」
「免許がないと生活ができなくなる!!!」
という強い希望をもったご高齢の患者様が、眼鏡やコンタクトの調整を目的に来院されるケースが増えています。
眼科スタッフとして、そのたびにA子はちょっと複雑な気持ちになります。
確かに、矯正視力が基準を満たせば免許は更新できます。それは法律上、正しいことです。
しかし――
「視力が出ている=安全に運転できる」
本当にそうでしょうか?
運転に必要なのは「視力」だけではありません
車の運転には、以下のような複数の能力が同時に必要です。
- 見えた情報を瞬時に理解する認知力
- 危険を予測して行動する判断力
- クラクションやサイレンに気づく聴力
- 体を素早く動かす反射・運動機能
眼科では「見える・見えない」は評価できます。
しかし、
- 認知機能のわずかな低下
- 耳が遠くなって音に気づくのが遅れること
- 反応が一拍遅れること
これらは視力検査だけでは分かりません。
「無理に通す」ことが本当に本人のためでしょうか?
免許を失う不安、車がない生活への不便さや恐れ。その気持ちはとてもよく分かります。家族の協力も得られにくいなど様々な事情があるのも十分理解はできます。
ですが、
- 歩行者が多い交差点
- 夕方以降や雨天などの暗い日
- 病院へ行く等、気持ちだけが急いでいるとき
- 急にスマホが鳴った
など、さまざまな状況が挙げられますが
もし判断が一瞬遅れたら?
その結果を背負うのは、本人だけではありませんよね?
このような場合、事故は「悪意」で起こそうとする人は滅多にいません。
「まだ大丈夫だと思っていた」
その積み重ねで起こります。
免許返納は「負け」ではありません
免許返納は
「もう何もできない」という宣言ではなく、「自分と周囲を守る選択」です。
実際に、
- 返納後に気持ちが楽になった
- 家族との関係が良くなった
- 公共交通や送迎を使うことで生活が安定した
という声も少なくありません。
眼科スタッフとして伝えたいこと
私たちは、
免許を“通すため”に視力を合わせる専門家ではありません。
患者様の生活全体の安全を考える医療従事者です。
「通るかどうか」ではなく、「続けるべきかどうか」を
今一度、本人も家族も一緒に考える時期に来ているのではないでしょうか。
最後に
運転をやめるタイミングは、人それぞれです。
しかし、
「まだ運転できる」時にこそ、やめる準備を始める
それが最も安全で、誇りある選択だと考えています。A子の親も実はまさに今、このタイミングなのです。是非一緒に考えてみませんか?