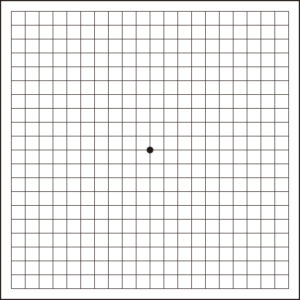目の奥が痛む、かすんで見えにくい、肩がこる、などの症状がある眼精疲労。 この眼精疲労の原因の一つにコレステロールがあると言われています。 目とはあまり関係がなさそうなコレステロールと、眼精疲労がなぜ関係があるのでしょうか?
コレステロール値が高いと、動脈硬化が引き起こされ、脳梗塞や心筋梗塞などの危険性が高まります。目の周りにも毛細血管がたくさんあるので、コレステロール値が高いとこの毛細血管も詰まってきてしまう恐れがあります。そのため目に十分な血液が送られなくなり、眼精疲労が引き起こされてしまうのです。
コレステロールとは細胞膜を生成する要素で、生きていく上では欠かすことのできない脂質の一種です。コレステロールと聞くとあまりよくないもの、というイメージがありますが、私たちの身体にはとても大切なものなので正常値を保てればいいのです。
コレステロールを下げる食べ物は野菜、大豆、魚貝、果物などです。 特に効果があると言われているのが、緑黄色野菜、シイタケ、青魚、りんご、コンニャクなどです。 これらの食品を献立に意識的に取り入れるようにして、コレステロール値を正常に保てるようにしたいものです。