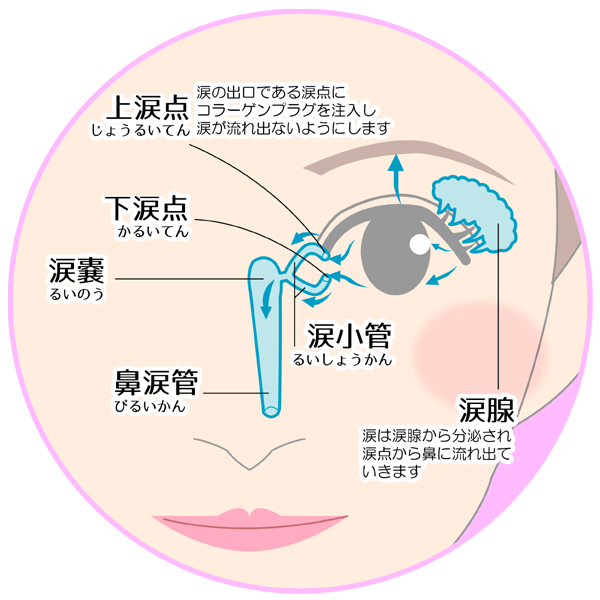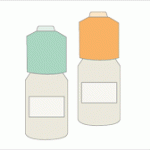仕事上はもちろん、パソコンやスマホの画面を長時間見ている方が大勢いらっしゃいます。最近では若い方でも目の疲れや、老眼のような症状を訴えるかたも多いのです。
 原因はこのような電子機器から発せられるブルーライトだといわれています。ブルーライトとは、人間が認識できる可視光線のなかで一番強いエネルギーの光で、目にも大変な負荷がかかるのです。
原因はこのような電子機器から発せられるブルーライトだといわれています。ブルーライトとは、人間が認識できる可視光線のなかで一番強いエネルギーの光で、目にも大変な負荷がかかるのです。
まずは電子機器の使用を必要最低限にするよう努力が必要ですが、仕事などでなかなか上手くいかないのも現実です。長時間画面を見なくてはならないような場合は「ブルーライトカット機能」のついたメガネを利用すると良いでしょう。
また、日常生活にはコンタクトレンズを利用しているという比較的若い世代の方であれば、このメガネを度無しにして併用します。視力はコンタクトレンズで矯正、ブルーライトはメガネで軽減。という使い方ができます。
少しでも目に対する負担が減るように、できるところから改善してみましょう!