【リジュランとは?】
リジュランとは「成長因子活性化」と「DNA再合成」という2つの効果をもち、有効成分として「PN(ポリヌクレオチド)」が高濃度で配合された肌の再生を目的とした注入療法のことです。また、PNとは鮭のDNAにより抽出された分子で、特許を取得した特殊技術で処理をすることにより人間の皮膚に最も高い適合性を持つことがわかっています。
 リジュランの働きとしては、
リジュランの働きとしては、
●皮膚の自己回復力の活性化させる
●真皮と表皮の厚み、全体的な皮膚のハリを改善させる
●若く健康的な皮膚の保持をする
といことが主なものです。加齢や外界からの刺激によるダメージを受けた肌は、肌の自己回復力が弱まっているためシワができやすくハリを失っている状態です。今まではフィラー剤でボリュームアップさせたり、レーザーなどで人工的な刺激を皮膚に与えることで肌細胞の再生をうながしてきました。
しかし、リジュランはこれらの従来の対処法とは異なり皮膚そのものの自己回復力を活性化させて皮膚のハリを改善させる治療となったのです。
【リジュランによる肌の10(テン)リフレッシュ】
リジュランを注入後、改善される10の効果・効能については4週間後が目の下および頬のハリに最も改善が見られることが多いです。
<リジュランの主な効果と効能について>
1) 密度とハリの改善
2) リフトアップ効果
3) 脂分と水分のバランスを整える
4) 毛穴の縮小
5) 皮脂の減少
6) 肌きめの改善
7) 小じわの改善
8) 肌の保護層の回復
9) くすみの改善
10) 角質の減少
【リジュランのダウンタイムについて】
お顔全体に注射をするため、注射をした直後から当日は施術部位が腫れる事がありますが、24時間以内には腫れはひきますので通常生活に戻ることができます。翌日がお休みでゆっくりできるというタイミングで施術を受けていただくことをお勧め致します。
【リジュランの安全性】
リジュランは生体適合性の高い物質であるため、有害な副作用が起きることはありません。※ただし、魚・魚卵などのアレルギーがある方は治療を控えて下さい。問診時に必ず食物アレルギー等がある方は院長にお申し出下さい。
肌年齢を10歳若くみせる「リジュラン」
料金については「1回の施術で1本注入¥35,000+税」「1回の施術で2本注入¥60,000+税」となっております。1回の施術で2本までが最大の注入量となります。
ご希望の方は、まずは予約不要の院長無料カウンセリングにてご相談ください。その際に麻酔の有無や施術予約の説明を行います。


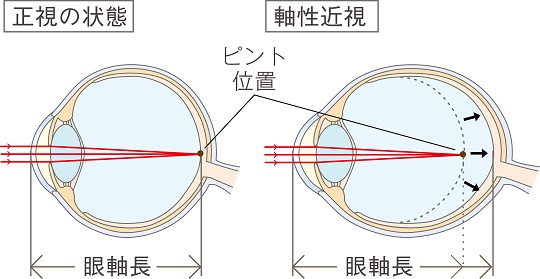
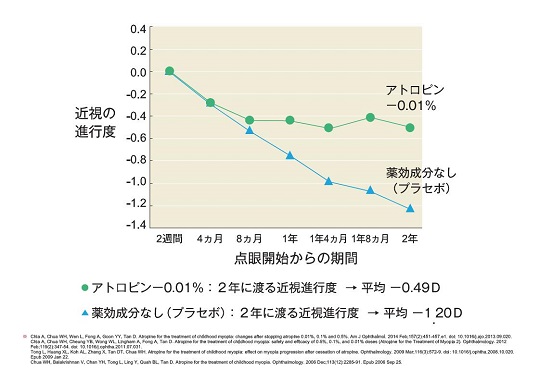



 子どもであれば裸眼視力が良好なことは大変喜ばしいことなのですが、強度の遠視が隠れているケースであれば治療を要することもあります。見たい対象がどの程度離れているかによっても見え方は変わってきます。
子どもであれば裸眼視力が良好なことは大変喜ばしいことなのですが、強度の遠視が隠れているケースであれば治療を要することもあります。見たい対象がどの程度離れているかによっても見え方は変わってきます。
