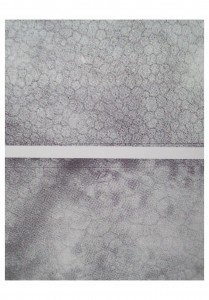学校健診で「D判定」だったら? 子どもの視力低下と心因性視力障害の話
学校の視力検査の結果を見て驚くことはありませんか。「D判定って何?」と慌てる親御さんは多いです。まずは落ち着いて、結果の意味と次に取るべき行動を確認しましょう。
まず確認したいこと:単純な近視の進行かどうか
多くの場合、D判定は単純に近視が進んだ結果です。メガネの度数を合わせ直せば視力が矯正できます。まずは眼科で検査を受け、適切な矯正視力(メガネをかけたときの視力)を確認しましょう。
矯正しても視力が出ない場合は要注意
もしメガネやコンタクトで矯正しても十分に視力が出ないときは、さまざまな要因を含めて詳しく調べる必要があります。
心因性視力障害とは?
今回は心因性についてとりあげてみます。「心因性視力障害」とは、心理的な影響で視力低下が生じる状態を指します。脳や目の明らかな器質的異常が見つからないのに、急に視力が落ちることがあります。原因は完全には解明されていませんが、子どものストレスや心理的な要因が関与していると考えられています。
心因性視力障害に見られる特徴
- 急に学校検診でD判定になった
- 視力低下は両眼に起こりやすい(0.3以下になることが多い)
- 視力検査で「全く見えない」と同じ答えばかり返す
- メガネをかけても矯正視力が出ない
- 小学3〜5年生の女児に多く見られる傾向がある
- 視野狭窄や色覚の訴えを伴うことがある
診断の流れと眼科で行うこと
- まずは眼科で精密検査(詳しい屈折検査、矯正視力測定、眼底検査など)を行います。
- 眼の機能的な問題(網膜や視神経の病気)がないかを確認します。
- 器質的な大きな異常がない場合は、経過観察や心理的側面の評価を検討します。
ご家族ができること(対処法)
- まずは否定せず、子どもの訴えに寄り添ってください。
- 学校や家庭でのストレス要因を探し、可能な範囲で軽減しましょう。
- 治療は時間がかかることがあります。焦らず、定期的に受診してください。
- 必要に応じて小児科や心理相談(スクールカウンセラー等)相談する事も選択肢の1つです。
いつ受診すべき?
学校検診でD判定が出たら、まず眼科で検査を受けてください。視力が急激に落ちている、痛みや見え方の変化がある場合は早めの受診をおすすめします。
最後に
学校健診でD判定だったからといって、すぐに深刻な問題があるとは限りません。しかし、矯正しても視力が出ない場合は必ず専門医に相談してください。原因の確認と、ご家庭での対応が大切です。当院でも丁寧に検査・相談を行っています。気になることがあればお気軽にご相談ください。