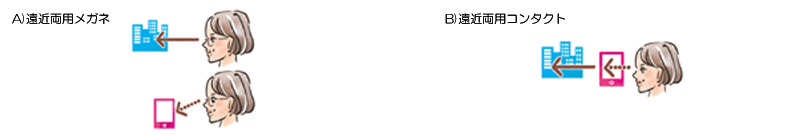目が悪いということを放置してしまうことはよくないことです。
例えばお子さんの場合だんだんと視力が低下していくと自分ではあまり気づかず、その見え方に慣れてしまい放置されてしまう可能性が高くなります。メガネなどで適正な視力に矯正して見えるようになると、今まで見えなかったものが見えて興味の幅も広がり、集中力も上がる可能性があります。
見えないということは学力や運動などにも悪い影響を与えてしまう恐れがあります。学校の視力検査でひっかかったら場合はそのままにせず、必ず眼科を受診するようにしてください。
もう一つ、視界がゆがんで見える、中心が見えにくい、かすむ、など突然見えにくくなったなどの症状が起きた場合は絶対に放置せず、すぐに病院に行きましょう。網膜剥離や緑内障、黄斑変性症など目の病気の可能性があるため、放置していると危険だからです。いつもと違う見え方、違和感を感じたら眼科を受診してください。
今年もあと4日になりました。年末年始お休みの方、お仕事の方、体調管理に気をつけて新しい年を迎えられるようにしたいですね。