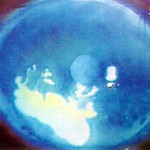ものもらいはほとんどの人が聞いたことがあるであろう有名な目の病気ですが、ものもらいには実は種類が2種類あります。
細菌感染によってできる「麦粒腫」は体調が悪く免疫力が低下している時や、汚い手で目をこすってしまった時などに感染を起こしてしまって、目が腫れてしまうものです。
もう一つのものもらい「霰粒腫」はまつげの生え際にあるマイボーム腺という部分に、脂が詰まってしまうことで起こる目の腫れのことをいいます。
ものもらいは一度完治したと思っても、繰り返してしまう人が多い病気です。
ものもらいになりやすい人には特徴があります。
*不規則な生活や寝不足、疲れやストレスなどで免疫力が弱ってしまっている人
*コンタクトレンズを正しく使用できていない人
*アイメイクをしっかり落とせていない人
*花粉症などアレルギーがある人に多い目をこすってしまう癖のある人
などが挙げられます。ものもらいを癖にしないために、バランスの良い食事と充分な睡眠をとって免疫力を高めることが大切です。
アイメイクがしっかり落とせていない人は、菌が繁殖して炎症を起こしてしまったり、メイクの落とし残りによってマイボーム腺が詰まってものもらいになってしまうなど、麦粒腫と霰粒腫両方の危険性があるので気をつけましょう。
ものもらいになってしまったら、ひどくなる前に病院でしっかり治すことが大切です。